白井智之
「白井くんの小説って、いつも誰か監禁されてるよね」
杉並区のアパートで同棲中の彼女が、ノートパソコンを覗き込んで言ったのは、この原稿を書いている今からちょうど一年前、「東京結合人間」の改稿作業が佳境を迎えていた頃のことだった。
ぼくはちょっとムキになって、「そんなことないよ」と答えた。でも彼女の言葉が胸に引っかかっていたぼくは、彼女が布団に入ってから、ノートパソコンに溜め込んだ過去の習作を読み返してみることにした。
高校三年生のとき、ぼくははじめて「スカッシュ・チルドレン」という短編を書いた。バナナ栽培が盛んな孤島で、七人のババアが殺されるという、端正な本格ミステリだ。目を通してみると、どういうわけか、ストーリーと無関係なところで老人が座敷牢に監禁されていた。
なんだこりゃと思いながら、大学時代に執筆した十余の習作を読み返して、ぼくは啞然とした。描写の大小は様々だったけれど、すべての作品で、ことごとく監禁事件が描かれていたのだ。中には、監禁された少女が衰弱死するだけの、なにが面白いのかよく分からない短編もあった。
小説家としてデビューしてからの作品も例外ではなかった。ぼくの処女作「人間の顔は食べづらい」には、地下室に監禁されたチャー坊というクローン人間が登場する。改稿中だった「東京結合人間」にも、売春グループに監禁され、暴行を受ける栞という少女が描かれていた。
そもそも、べつにぼくは、監禁というテーマが好きで小説家を志したわけではない。意図しないところで、監禁事件を描き続けていたのだ。我ながら、自分の深層心理が怖くなった。
「フロイトとかユングとかが大喜びしそうなはなしだね。ちっちゃいころ、何かあったんじゃないの?」
翌朝、ぼくが奇妙な発見について打ち明けると、彼女は楽しげに答えた。いつもぼくの部屋でごろついている彼女だが、じつは文学部で心理学を専攻していて、「精神分析入門」なんかを愛読していた。
気味が悪いと思いながらも、このときは深く考えることをしなかった。けれど一年過ぎて、講談社文三出版部のモリタさんから「日常の謎」をテーマにしたエッセイの依頼を受けたので、あらためてこの不思議を掘り返してみることにした。
心理学や精神分析は門外漢なので、専門家に意見を聞くのが早いだろう。ぼくは友人で臨床心理士のイトダくんに相談してみることにした。
「科学的な見解じゃないから、話半分に聞いてね。白井が幼少期に監禁されていたことがある――ってのはさすがに短絡的だけど、それに近い体験をしている可能性はあるね。あるいは、身近なところで監禁事件が起きたとか。同じ体験をしたいって願望が、白井の中にあるんだよ」
フリースクールや児童相談所でもカウンセリングをしているというイトダくんは、真剣な表情でそう言った。
「逆でしょ? トラウマがあって、監禁への恐怖があるんだと思ってたけど」
「だったらフラッシュバックとか睡眠障害とか、分かりやすい症状が出るはずだよ。強制されたんじゃなく、自分で小説を書いたんでしょ。白井は、誰かが自分を誘拐して、代わり映えしない日常を終わらせてくれるのを期待してるんだよ」
なるほど、ぼくの中にはずいぶんと特殊な欲求が隠れていたらしい。というかマゾだ。
とはいえ、幼いころ身近に監禁事件が起きていた可能性は高いようだ。ぼくは続けて、幼少からの友人であるクリヤマくんに話を聞いてみることにした。
「お前、彼女いんの? 白井なのに?」
クリヤマくんは本題と無関係なところに食いついてきた。うるせえよ。
「小さいころ、近くで監禁とか誘拐とかなかったっけ?」
「ないない。こんな田舎で監禁事件なんてあったら、みんなにすぐ知れ渡るはずだよ。ほら、セガワの父ちゃんが詐欺で捕まったときも、すぐ広まったじゃん」
やはり心当たりはなさそうだ。続けて何人かの友人に話を聞いてみたけれど、答えは似たり寄ったりだった。
その晩、彼女に調査結果を教えると、
「そんなもんでしょ。白井くんが小説を書くときに、定型のパターンを使い回してただけじゃないの」
彼女は退屈そうに「精神分析入門」をめくりながら言った。
一週間後、ぼくは祖父の三回忌のため地元の千葉へ帰った。白井家の菩提寺はもともと新潟にあったのだが、手入れをする親族がいなくなったため、父が千葉へ墓を移したのだ。
法要を終えた帰りぎわ、母に同じ質問をぶつけてみると、母は目を丸くして言った。
「覚えてないの? もう十五年くらい前だけど、新潟で有名な監禁事件があったでしょ。九年間、自宅の二階に女の子を監禁してたやつ。あんた、九歳のころ新潟へ遊びに行って、犯人に会ってるんだよ。公園でコワそうな男に話しかけられたのを、あたしが連れ戻したの。一年後に犯人が捕まったとき、あんたもびっくりしてたじゃない」
ぼくは耳を疑った。言われてみると、夕暮れ時に禿頭の男に声をかけられた記憶が、ぼんやりと残っていた。
オチとしてあまりにできすぎだが、これが真相に違いない。九歳のころ監禁犯に接触した記憶が、自分も監禁されたいという歪んだ欲求に代わり、ぼくに監禁をテーマにした小説を書かせていたのだ。
「あと、これは最近のことだから関係ないだろうけど」
母が思いついたように付け足した。
「あんたが小学生のときに同級生だった、セガワシオリちゃんっていたでしょ。あの子、一年半前から行方不明らしいよ。ほら、早稲田の文学部で心理学をやってた子。無事だといいけどねえ」
母が不安そうに顔を曇らせる。ぼくは適当に気休めの言葉をかけて、杉並区のアパートへと足を急いだ。
- 『腐れ縁』 最東対地
- 『九本指』 山吹静吽
- 『忘れられた犯人』 阿津川辰海
- 『ささやき』 木犀あこ
- 『普通と各停って、違うんですか』 山本巧次
- 『雨の日の探偵』 階 知彦
- 『神々の計らいか?』 吉田恭教
- 『虫』 結城充考
- 『監禁が多すぎる』 白井智之
- 『チョコレートを嫌いになる方法』 辻堂ゆめ
- 『銀河鉄道で行こう!』 豊田巧
- 『方向指示器』 小林泰三
- 『庭をまもるもの』 須賀しのぶ
- 『寅さんの足はなぜ光る』 柴田勝家
- 『脱走者の行方』 黒岩 勉
- 『日常の謎の作り方』 坂木 司
- 『味のないコーラ』 住野よる
- 『鍵のゆくえ』 瀬川コウ
- 『彼らはなぜモテるのだろうか……』 市川哲也
- 『やみのいろ』 中里友香
- 『インデックス化と見ない最終回』 十市 社
- 『文系人間が思うロボットの不思議』 沢村浩輔
- 『街道と犬ども』 石川博品
- 『沖縄のてーげーな日常』 友井 羊
- 『ジャンルという名の妖怪たち』 ゆずはらとしゆき
- 『カロリー表示は私を健康に導くのか』 秋川滝美
- 『終電を止める女』 芦沢 央
- 『女子クラスにおける日常の謎』 櫛木理宇
- 『IBSと遅刻癖』 岡崎琢磨
- 『シューズ&ジュース』 青崎有吾
- 『キャラが立つとは?』 東川篤哉
- 『「源氏物語」のサブカルな顔』 荻原規子
- 『そこにだけはないはずの』 似鳥 鶏
- 『『美少女』に関する一考察』 加賀美雅之
- 『食堂Kの謎』 葉真中顕
- 『寒い夏』 ほしおさなえ
- 『人喰い映画館』 浦賀和宏
- 『あやかしなこと』 平山夢明
- 『あなたの庭はどんな庭?』 日明 恩
- 『日常の謎がない謎』 小松エメル
- 『影の支配者』 小島達矢
- 『「五×二十」』 谷川 流
- 『グレープフルーツとお稲荷さん』 阿部智里
- 『ボールペンを買う女』 大山誠一郎
- 『日常の謎の謎』 辻真先
- 『『サイバー空間におけるデータ同定問題』あるいはネット犯罪量産時代』 一田和樹
- 『囲いの中の日常』 門前典之
- 『カレーライスを注文した男』 岸田るり子
- 『お前は誰だ?』 丸山天寿
- 『世界を見誤る私たち』 穂高 明
- 『名探偵は日常の謎に敵うのかしら?』 相沢沙呼
- 『で、あなた何ができるの?はあ、皇帝だったらたぶん…』 秋梨惟喬
- 『すっぽんぽんでいこう!』 桜木紫乃
- 『右腕の長い男』 麻見和史
- 『坂道の上の海』 七河迦南
- 『彼女は地下鉄でノリノリだった、という話。』 柴村仁
- 『その日常で大丈夫か?』 汀こるもの
- 『成功率百パーセントのダイエット』 小前亮
- 『謎の赤ん坊』 蒲原二郎
- 『一般人の愚痴と疑問』 沼田まほかる
- 『寄る怪と逃げる怪』 高田侑
- 『福の神』 木下半太
- 『マッドサイエンティストへの恋文』 森深紅
- 『私の赤い文字』 大山尚利
- 『となりあわせの君とリセット』 詠坂雄二
- 『美人はなぜ美人なのか』 小川一水
- 『なぜモノがあるのか。』 鈴木光司
- 『この目で見たんだ』 北村薫
- 『運命の糸が赤いのは?』 山下貴光
- 『念力おばさん』 湊かなえ
- 『方向オンチはなぜ迷う?』 山本弘
- 『ゆがむ顔のカルマ』 真藤順丈
- 『子供だけが知っている』 宇佐美まこと
- 『人はなぜ、酒を飲むのか』 薬丸岳



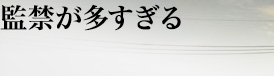
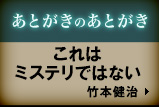


 メフィスト 2020 vol.2
メフィスト 2020 vol.2 メフィスト 2020 vol.1
メフィスト 2020 vol.1 メフィスト 2019 vol.3
メフィスト 2019 vol.3 メフィスト 2019 vol.2
メフィスト 2019 vol.2 メフィスト 2019 vol.1
メフィスト 2019 vol.1 メフィスト 2018 vol.3
メフィスト 2018 vol.3 メフィスト 2018 vol.2
メフィスト 2018 vol.2 メフィスト 2018 vol.1
メフィスト 2018 vol.1 メフィスト 2017 vol.3
メフィスト 2017 vol.3 メフィスト 2017 vol.2
メフィスト 2017 vol.2 メフィスト 2017 vol.1
メフィスト 2017 vol.1 メフィスト 2016 vol.3
メフィスト 2016 vol.3 メフィスト 2016 vol.2
メフィスト 2016 vol.2 メフィスト 2016 vol.1
メフィスト 2016 vol.1 メフィスト 2015 vol.3
メフィスト 2015 vol.3 メフィスト 2015 vol.2
メフィスト 2015 vol.2 メフィスト 2015 vol.1
メフィスト 2015 vol.1 メフィスト 2014 vol.3
メフィスト 2014 vol.3 メフィスト 2014 vol.2
メフィスト 2014 vol.2 メフィスト 2014 vol.1
メフィスト 2014 vol.1 メフィスト 2013 vol.3
メフィスト 2013 vol.3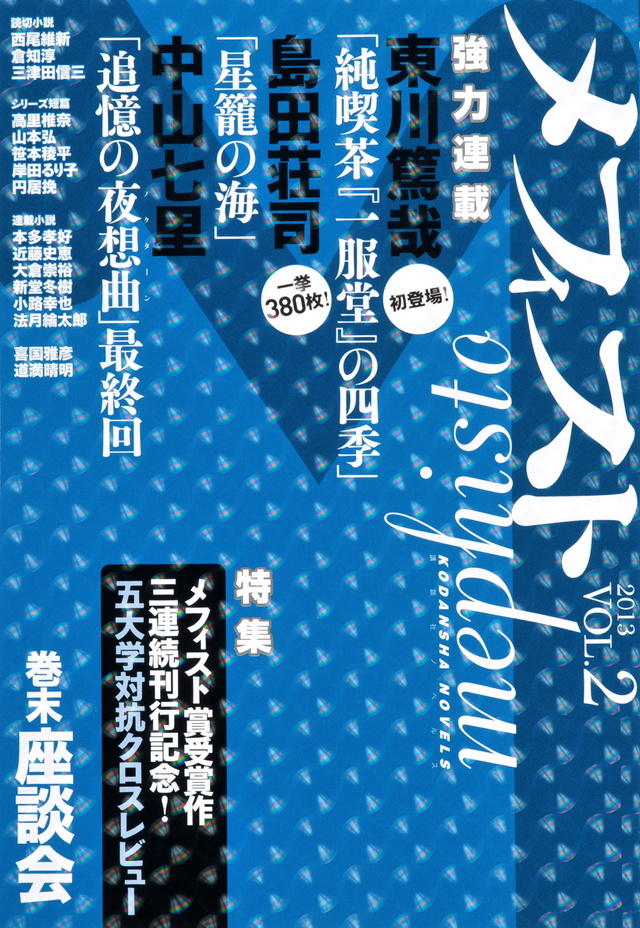 メフィスト 2013 vol.2
メフィスト 2013 vol.2 メフィスト 2013 vol.1
メフィスト 2013 vol.1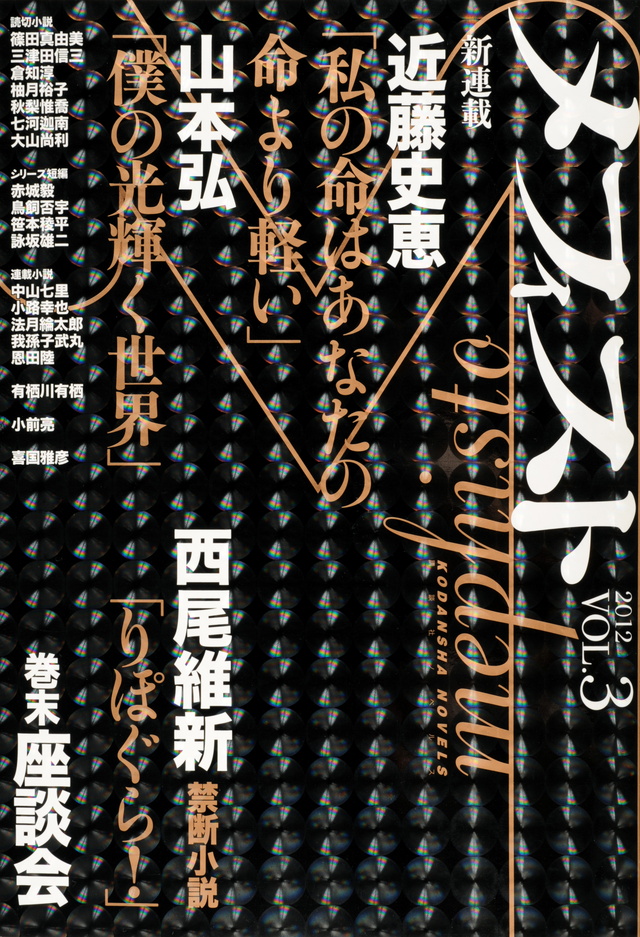 メフィスト 2012 vol.3
メフィスト 2012 vol.3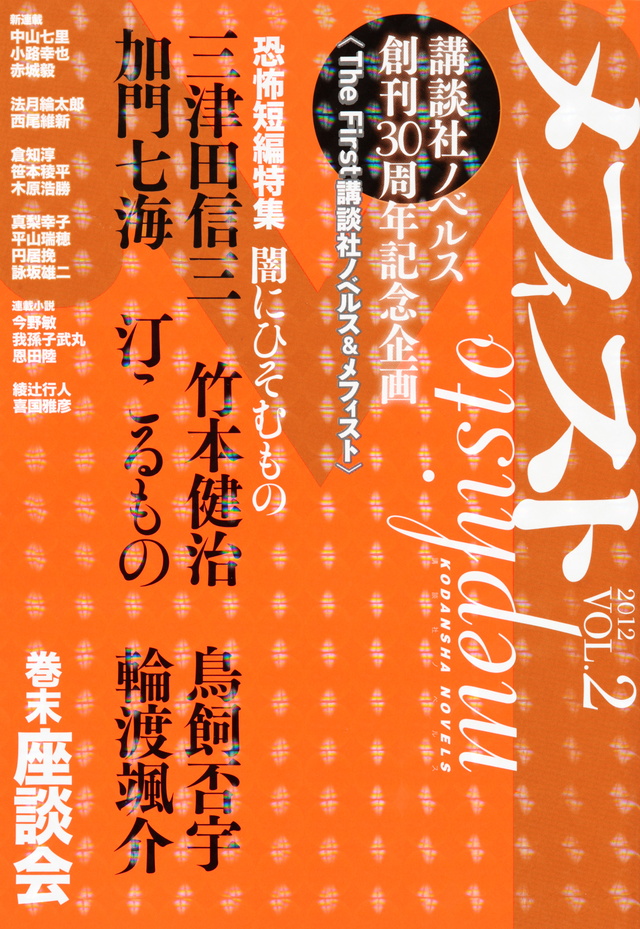 メフィスト 2012 vol.2
メフィスト 2012 vol.2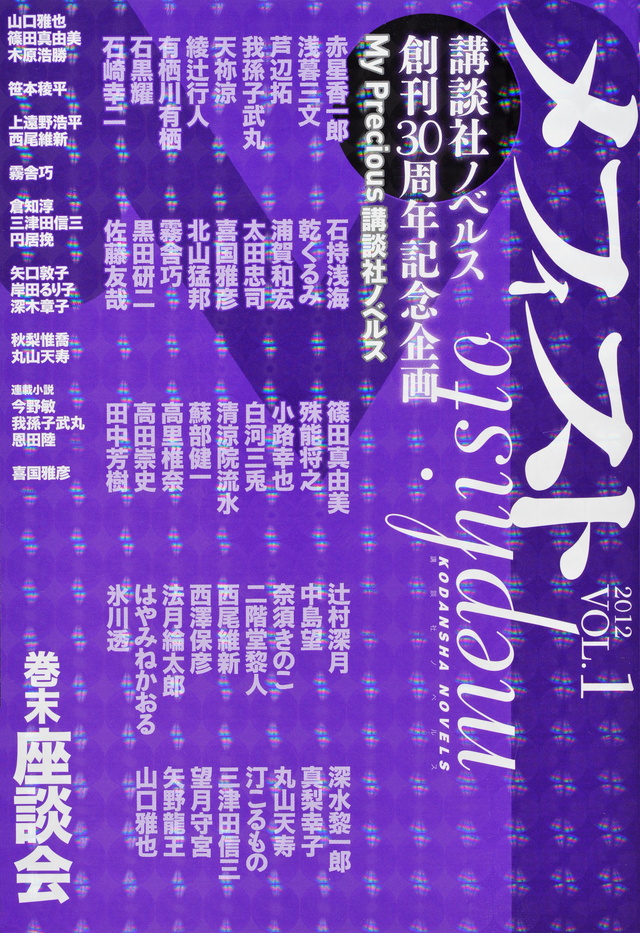 メフィスト 2012 vol.1
メフィスト 2012 vol.1 メフィスト 2011 vol.3
メフィスト 2011 vol.3 メフィスト 2011 vol.2
メフィスト 2011 vol.2 メフィスト 2011 vol.1
メフィスト 2011 vol.1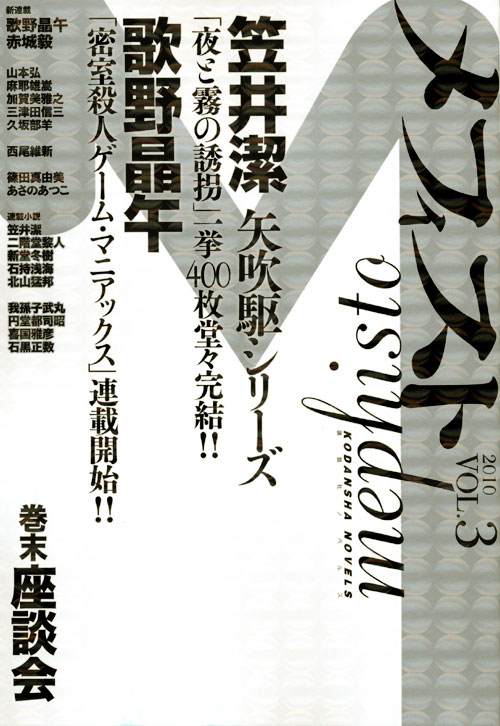 メフィスト 2010 vol.3
メフィスト 2010 vol.3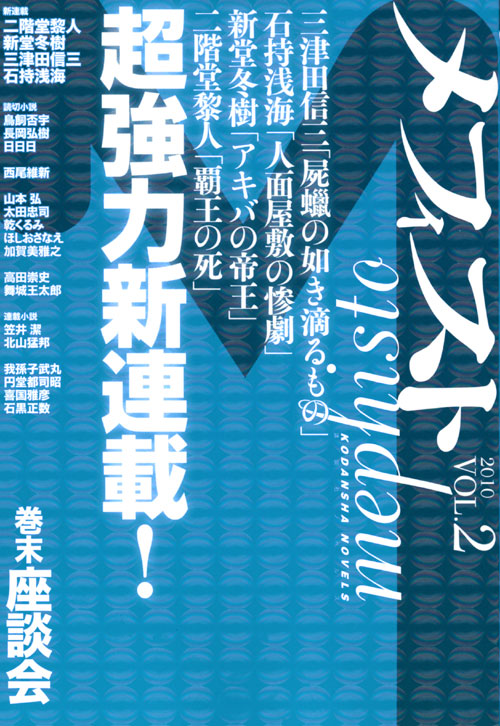 メフィスト 2010 vol.2
メフィスト 2010 vol.2 メフィスト 2010 vol.1
メフィスト 2010 vol.1 メフィスト 2009 vol.3
メフィスト 2009 vol.3 メフィスト 2009 vol.2
メフィスト 2009 vol.2 メフィスト 2009 vol.1
メフィスト 2009 vol.1




