芦沢 央(あしざわ よう)
生まれてきてよかった、と思うことが度々ある。
いいこと続きだからではない。私はお酒を焼酎なら三杯、ワインなら二杯飲むと大抵そうした心持ちになるのだ。
好物のサーモンを肴に少量のお酒をあおっているだけで世界が輝いて感じられ、一緒にいる人がいい人に見え、生まれてきてよかったと心から思えるのだから、我ながら安上がりで幸せな体質である。
だが、決してお酒に強いわけでもないので失敗談も尽きない。ほろ酔いで電車に乗ってふと気づいたら成田空港や東武動物公園にいた、というのはまだ潜在願望をうかがわせるかわいげのある失敗だが、財布を落とすこと三回、鍵を失なくすこと五回、鞄ごと紛失すること二回、となると少々笑えない(人には笑われるが)。
また、これは結婚してからの話なのだが、酔って帰宅して玄関で眠ってしまったこともある。それも、どうやら風呂と玄関を間違えたらしく半裸で玄関に向かって倒れていたそうだ。翌朝起きてきた家人が恐る恐る私に触れると冷えきっていたので(まだ肌寒い時節だった)、思わず「し、死んでる……!」とお約束のセリフを口にしてしまったという。
玄関のドアまで辿り着けなくてよかった。これが外に出て行き倒れた姿を隣人に発見されていたら本当に死体になってしまいたくなっただろう。
そうしたわけで、お酒は大好きなものの家人から「くれぐれも控えよ」と申し渡されているのだが、今回紹介したいのは失敗談ではない。大学生の頃、酔って乗った終電で見知らぬ駅に辿り着き、「はて、ここは……」とホームで立ち尽くしていた私が目撃した謎の女についてだ。
私がその女に気づいたのは、『ドアを閉めます! 発車します!』とアナウンスが繰り返されるも一向にドアが閉まらず発車もしないのを訝しく思って電車を振り返ったからだった。
原因はすぐに見つかった。一組の男女がドアの間近で揉み合っていたのである。すわ痴漢かと身構えたが、どうもそうではないらしい。
「いいから帰るぞ!」
「いや! 帰らない!」
二人のセリフが聞こえてくるや、脳みそが幸せな状態になっていた私は、いいねえラブラブだねえ、とニヤついた。
男の方は帰りたがっているようだが、翌朝に予定があったり宿泊費が足りなかったりするのだろうか――そう憶測を巡らせていると、男が女を車内に引きずり込み始めた。女は膝立ちになってドアにしがみつく。突然激しさを増した展開に、乗客たちは何事かと身を乗り出し、駅員の『危ないですから乗るか降りるかしてください!』という声にも切迫感が混じり出した。
乗客や駅員のように直接の被害があるわけではない、むしろ完全に無関係な私も、行く末を見届けねば立ち去れない気がしてくる。
と、ついに女がホームへと転がり出た。
「早く乗れよ!」
男もそう叫ぶだけで追おうとはしない。その隙を突いたようにドアが閉まる。男と女はガラス越しに顔を見合わせた。
電車はゆっくりと滑り出し、ホームには靴の脱げた女と野次馬根性丸出しの私だけが残された。
電車がホームから離れても女は座り込んだまま動こうとしない。大丈夫だろうか――私が足を踏み出した途端、女は勢いよく立ち上がった。そのまま何事もなかったかのように靴を履き直し、スタスタと歩き始める。鞄から携帯を取り出して慣れた仕草で耳に当てた。
「もしもしユウくん? もうほんと恥ずかしかったよー。超注目の的だし。こんなことしてあげるの私くらいだからね?」
それまでの感情的なわめき声とは別人のように、間延びした笑いを含んでいる。啞然と立ち尽くした私を置いて、女は改札へ続く階段に消えた。
――今のは何だったのだろう。
電話の相手はたった今電車に乗っていった彼なのか? それとも全くの別人? 「ユウくん」ということは男性なのだろうが、「こんなことしてあげるの」というセリフは一体――。
そこで私はハッと息を吞んだ。彼女はこの状況について何の説明もしていない。にもかかわらず、相手には状況が伝わっているようではなかったか。
先ほどの彼が「ユウくん」なのだとしたら状況を把握していても不思議はないが、だとすると口調の変化が腑に落ちない。まさか先ほどのやり取りは二人で示し合わせた演技だったとでもいうのだろうか。だが、何のために?
あるいは、「ユウくん」が先ほどの男とは別人だとすればどうだろう。その場合、彼はこの状況を目撃できる場所にいたか、そうでなければ予めこうなることを知っていたということになる。それは何を意味するのか――?
わからない。想像することはできるが――たとえば、あの男女は人間観察を趣味としていて、痴話喧嘩を目の当たりにした人々の反応を楽しんでいたのだとか、「ユウくん」はどうしても終電に乗りたいけれど間に合わなさそうだから彼女に電車を引き留めておくように頼んだとか――それが正解かどうかを知る術はない。
ミステリのように「探偵」が解答を示してくれるわけでも、「犯人」が自白してくれるわけでもないからだ。
一人、あるいは二人の男と女の関係はどんなもので、何が彼女にああした言動を取らせたのか――それは謎のままだ。「女は謎」で片づけてしまえば終わりなのだが、私は自身も女だからかそう割り切ることができない。いや、本当のところ私はそうした「女の謎」に魅せられているのだ。強さと弱さ、賢さと愚かしさがないまぜになった性――そしてその奥にある尽きない欲望に。そうした人間の業のようなものと向き合うために、私は小説を書いているのかもしれない。
- 『腐れ縁』 最東対地
- 『九本指』 山吹静吽
- 『忘れられた犯人』 阿津川辰海
- 『ささやき』 木犀あこ
- 『普通と各停って、違うんですか』 山本巧次
- 『雨の日の探偵』 階 知彦
- 『神々の計らいか?』 吉田恭教
- 『虫』 結城充考
- 『監禁が多すぎる』 白井智之
- 『チョコレートを嫌いになる方法』 辻堂ゆめ
- 『銀河鉄道で行こう!』 豊田巧
- 『方向指示器』 小林泰三
- 『庭をまもるもの』 須賀しのぶ
- 『寅さんの足はなぜ光る』 柴田勝家
- 『脱走者の行方』 黒岩 勉
- 『日常の謎の作り方』 坂木 司
- 『味のないコーラ』 住野よる
- 『鍵のゆくえ』 瀬川コウ
- 『彼らはなぜモテるのだろうか……』 市川哲也
- 『やみのいろ』 中里友香
- 『インデックス化と見ない最終回』 十市 社
- 『文系人間が思うロボットの不思議』 沢村浩輔
- 『街道と犬ども』 石川博品
- 『沖縄のてーげーな日常』 友井 羊
- 『ジャンルという名の妖怪たち』 ゆずはらとしゆき
- 『カロリー表示は私を健康に導くのか』 秋川滝美
- 『終電を止める女』 芦沢 央
- 『女子クラスにおける日常の謎』 櫛木理宇
- 『IBSと遅刻癖』 岡崎琢磨
- 『シューズ&ジュース』 青崎有吾
- 『キャラが立つとは?』 東川篤哉
- 『「源氏物語」のサブカルな顔』 荻原規子
- 『そこにだけはないはずの』 似鳥 鶏
- 『『美少女』に関する一考察』 加賀美雅之
- 『食堂Kの謎』 葉真中顕
- 『寒い夏』 ほしおさなえ
- 『人喰い映画館』 浦賀和宏
- 『あやかしなこと』 平山夢明
- 『あなたの庭はどんな庭?』 日明 恩
- 『日常の謎がない謎』 小松エメル
- 『影の支配者』 小島達矢
- 『「五×二十」』 谷川 流
- 『グレープフルーツとお稲荷さん』 阿部智里
- 『ボールペンを買う女』 大山誠一郎
- 『日常の謎の謎』 辻真先
- 『『サイバー空間におけるデータ同定問題』あるいはネット犯罪量産時代』 一田和樹
- 『囲いの中の日常』 門前典之
- 『カレーライスを注文した男』 岸田るり子
- 『お前は誰だ?』 丸山天寿
- 『世界を見誤る私たち』 穂高 明
- 『名探偵は日常の謎に敵うのかしら?』 相沢沙呼
- 『で、あなた何ができるの?はあ、皇帝だったらたぶん…』 秋梨惟喬
- 『すっぽんぽんでいこう!』 桜木紫乃
- 『右腕の長い男』 麻見和史
- 『坂道の上の海』 七河迦南
- 『彼女は地下鉄でノリノリだった、という話。』 柴村仁
- 『その日常で大丈夫か?』 汀こるもの
- 『成功率百パーセントのダイエット』 小前亮
- 『謎の赤ん坊』 蒲原二郎
- 『一般人の愚痴と疑問』 沼田まほかる
- 『寄る怪と逃げる怪』 高田侑
- 『福の神』 木下半太
- 『マッドサイエンティストへの恋文』 森深紅
- 『私の赤い文字』 大山尚利
- 『となりあわせの君とリセット』 詠坂雄二
- 『美人はなぜ美人なのか』 小川一水
- 『なぜモノがあるのか。』 鈴木光司
- 『この目で見たんだ』 北村薫
- 『運命の糸が赤いのは?』 山下貴光
- 『念力おばさん』 湊かなえ
- 『方向オンチはなぜ迷う?』 山本弘
- 『ゆがむ顔のカルマ』 真藤順丈
- 『子供だけが知っている』 宇佐美まこと
- 『人はなぜ、酒を飲むのか』 薬丸岳



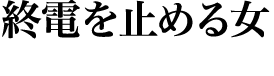
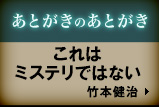


 メフィスト 2020 vol.2
メフィスト 2020 vol.2 メフィスト 2020 vol.1
メフィスト 2020 vol.1 メフィスト 2019 vol.3
メフィスト 2019 vol.3 メフィスト 2019 vol.2
メフィスト 2019 vol.2 メフィスト 2019 vol.1
メフィスト 2019 vol.1 メフィスト 2018 vol.3
メフィスト 2018 vol.3 メフィスト 2018 vol.2
メフィスト 2018 vol.2 メフィスト 2018 vol.1
メフィスト 2018 vol.1 メフィスト 2017 vol.3
メフィスト 2017 vol.3 メフィスト 2017 vol.2
メフィスト 2017 vol.2 メフィスト 2017 vol.1
メフィスト 2017 vol.1 メフィスト 2016 vol.3
メフィスト 2016 vol.3 メフィスト 2016 vol.2
メフィスト 2016 vol.2 メフィスト 2016 vol.1
メフィスト 2016 vol.1 メフィスト 2015 vol.3
メフィスト 2015 vol.3 メフィスト 2015 vol.2
メフィスト 2015 vol.2 メフィスト 2015 vol.1
メフィスト 2015 vol.1 メフィスト 2014 vol.3
メフィスト 2014 vol.3 メフィスト 2014 vol.2
メフィスト 2014 vol.2 メフィスト 2014 vol.1
メフィスト 2014 vol.1 メフィスト 2013 vol.3
メフィスト 2013 vol.3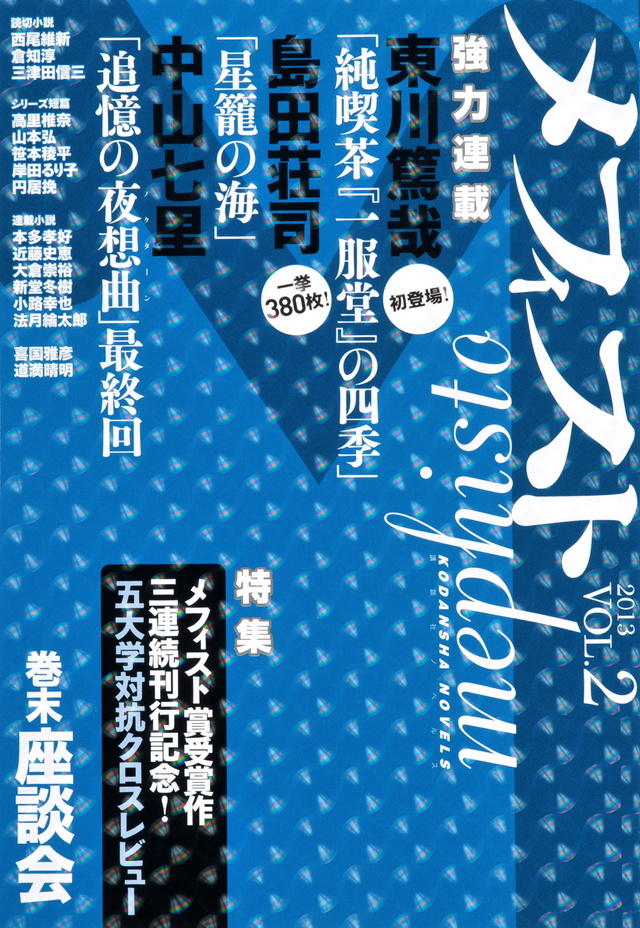 メフィスト 2013 vol.2
メフィスト 2013 vol.2 メフィスト 2013 vol.1
メフィスト 2013 vol.1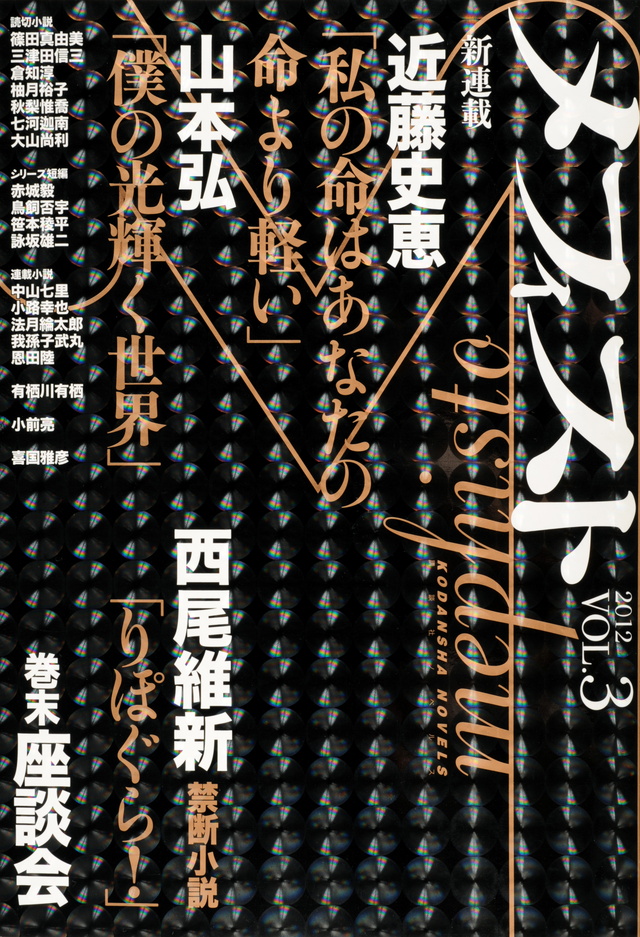 メフィスト 2012 vol.3
メフィスト 2012 vol.3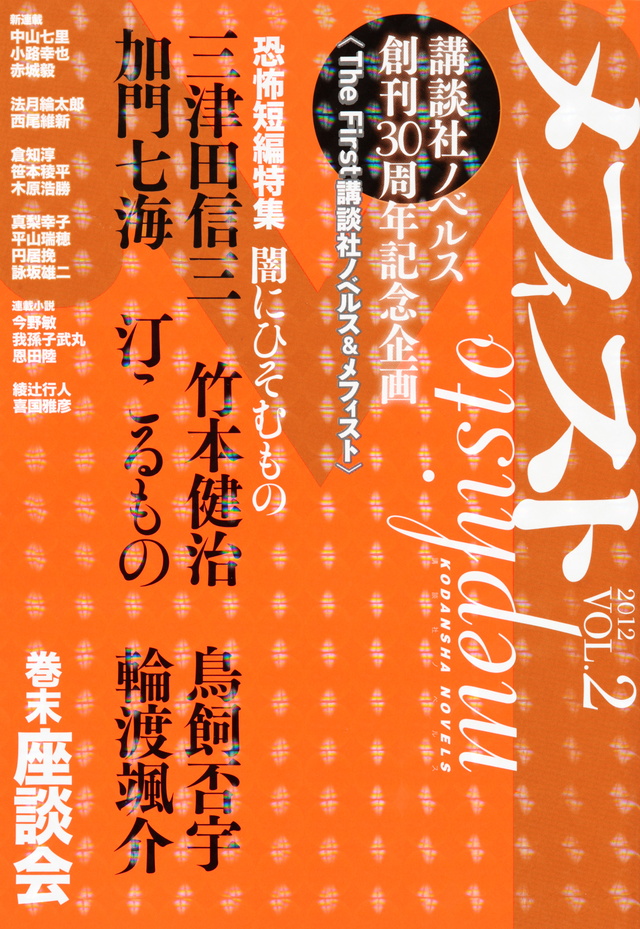 メフィスト 2012 vol.2
メフィスト 2012 vol.2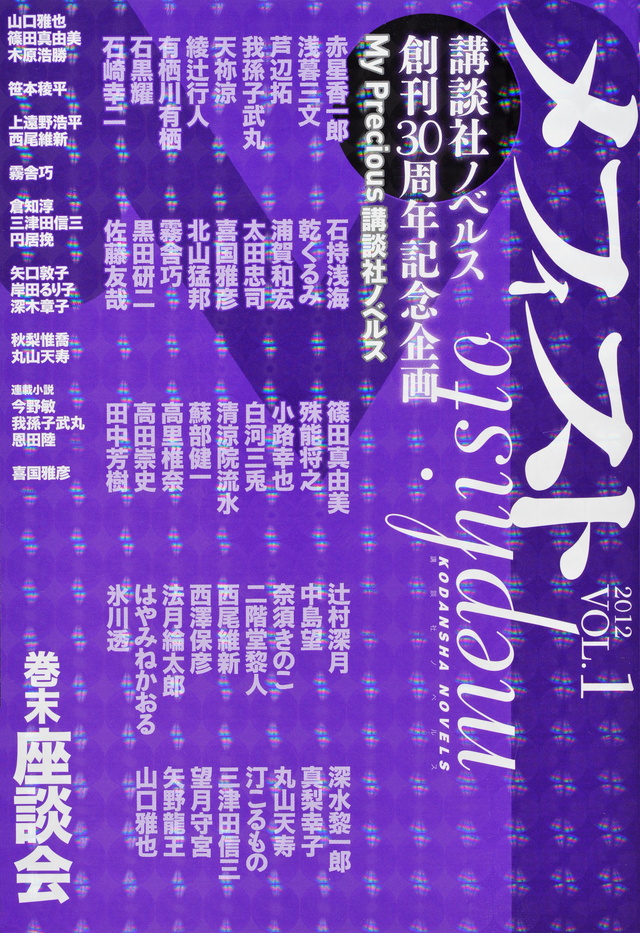 メフィスト 2012 vol.1
メフィスト 2012 vol.1 メフィスト 2011 vol.3
メフィスト 2011 vol.3 メフィスト 2011 vol.2
メフィスト 2011 vol.2 メフィスト 2011 vol.1
メフィスト 2011 vol.1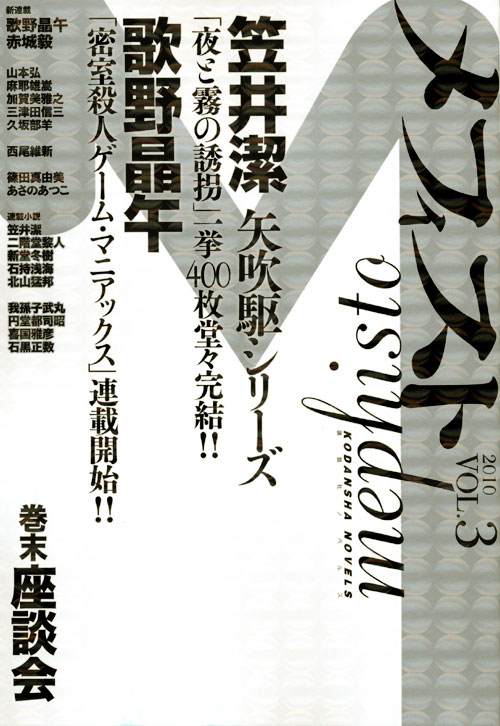 メフィスト 2010 vol.3
メフィスト 2010 vol.3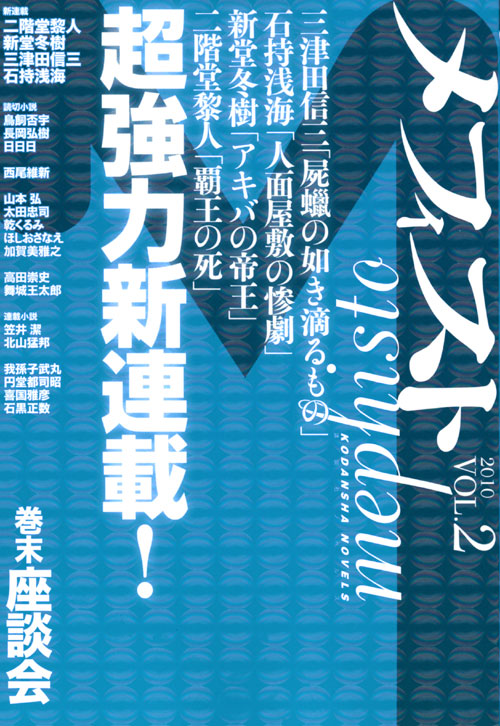 メフィスト 2010 vol.2
メフィスト 2010 vol.2 メフィスト 2010 vol.1
メフィスト 2010 vol.1 メフィスト 2009 vol.3
メフィスト 2009 vol.3 メフィスト 2009 vol.2
メフィスト 2009 vol.2 メフィスト 2009 vol.1
メフィスト 2009 vol.1




