麻見和史(あさみ かずし)
大学一年の秋だったと思うが、ジャケットを買おうと決め、紳士服店に行った。懐が寒いので高い品は買えない。ほどほどの値段で、そこそこに見えるものを選んだ。
袖丈を直すのに採寸してもらったのだが、このとき、
「お客さん、右腕のほうが長いですね」
と言われてびっくりした。
それまで、一度も気にしたことはなかった。そうなのか、自分は右腕の長い男だったのかと、少なからずショックを受けた。
「うーん。自分じゃ全然気がつきませんでしたけど……」
私が困ったような顔をすると、相手は笑って、
「そういう方、けっこういますから」
と慰めるように言ってくれた。採寸のプロが言うならそうなのだろうと思い、私は、左右の袖の長さが少し違うジャケットを持って帰った。
帰宅してあらためて鏡を見ると、たしかに右腕の指先のほうが、左の指先より下にある。いや待て、これは肩が下がっているせいではないのか?
普通に気をつけの姿勢でいてもバランスが悪く、明らかに右の肩が落ちている。このことは前から意識していたが、そのせいで「右腕の長い男」に認定されるとは思わなかった。
なぜ右肩が下がっているのか、考えてみた。思い当たる節はある。よくない姿勢で長時間、文字を書き続けていたせいだろう。
話は中学生時代にさかのぼる。
十三、四のころから、大学ノートに小説もどきのものを書いていた。当時はSFが好きで、人類が宇宙に進出する物語をいくつも書いたが、なぜか多くの作品で人類が滅んでいた。どれも拙い出来で、今読んだら噴飯ものだろうと思う。
高校に入ってからは、少しまともな話を作るようになったが、相変わらず人類は滅亡しがちだった。時間もののSFでは、宇宙そのものが消滅しそうになった。深夜にコーラを飲み、甘い菓子を食べながら、終末SFばかりを書いていたのだ。虫歯の多い、この上なくインドア指向の高校生だった。思うように創作が進まないと、歯噛みして悔しがったりした。
そして大学。相変わらずノートいっぱいに荒唐無稽な物語を書いていた。このころにはミステリーや純文学らしきものにも手を出して、机上は混沌とした状態になっていた。誰に読ませるわけでもないのに、とにかく書き続けた。
もともと筆圧が強かったため、ガリ版を作るような調子で書いていたのだと思う。それを毎日続けたのだから、右腕には相当の負担がかかったはずだ。おまけにたいそう姿勢が悪い。それで徐々に右肩が下がり、「右腕のほうが長いですね」と言われたのではないか――。大学生だった私は、そのように考えた。
今の時代なら、事情は違っていただろう。みな執筆にはパソコンを使い、軽快にキーボードを叩く。多少姿勢が悪くても、左右の腕にそれほど負荷の違いは生じないように思う。
社会人になってから、私もパソコンを使うようになった。家人が詳しかったから、見よう見まねで触るようになったのだ。といっても表計算をするわけではなく、やはり小説もどきを書くのに使った。出来た作品をプリントアウトすると、たいそう美しい仕上がりになる。「これは傑作ではないか」と誤解することが増えた。大学ノートの出番はなくなり、強い筆圧でものを書く機会も減っていった。
それでも鏡を見ると、相変わらず体のバランスは悪かった。まあ、長く続けた趣味のせいだし、仕方がない。気にすることはないだろう、と思っていた。
ところが、最近になって衝撃的な事実を知ったのだ。私の右腕が長い―正確には右肩が少し下がっている―のは、長らく小説を書き続けていたせいではないらしい。
西原克成著『顔の科学―生命進化を顔で見る』(日本教文社)にそのことが書かれていた。食物を咀嚼するとき、右側ばかりで噛む癖があると、脊椎が変形して右肩が下がるという。たしかに自分は右側でものを噛むことが多かった。同書に掲載された人体図を見ると、まさに自分の体型にそっくりだった。
なんということだ。私の右腕が長かったのは、右の噛み癖のせいだったのだ。さらにさかのぼれば、左の奥歯が丈夫でなかったから、ということになるだろう。高校生のころ虫歯の治療をしたのだが、詰め物の状態がよくなかったため、左側で噛むのを避けていたのだ。
左で噛むようにすれば、矯正の可能性はあるらしい。しかしこうなってから、かなりの年月がたっている。なかなか元には戻らないのではないか。とりあえず、思い出したときには左で噛むようにしているが、どれぐらい効果があるかはわからない。
まあいいか、という気持ちもある。右腕が少し長いからといって、痛みやかゆみがあるわけではない。少し肩が凝りやすいかな、と思うぐらいだ。
そういうわけで私はずっと「右腕の長い男」のままでいる。その腕でキーボードを叩き、ミステリーを書いてきた。運よく新人賞を受賞し、縁あって、このたび『石の繭 警視庁捜査一課十一係』を講談社ノベルスのラインアップに加えていただくことも決まった。石の上にも三年、という言葉を思い出す。いや、実際には三年どころではなかったけれど。
現在、日常生活にこれといった支障はない。ただ、一点だけ気をつけているのは、写真を撮ってもらうとき、心持ち右肩を上げるようにすること。それを忘れると、締まりのない人間に見えてしまって、どうにも恰好がつかないのだ。
- 『腐れ縁』 最東対地
- 『九本指』 山吹静吽
- 『忘れられた犯人』 阿津川辰海
- 『ささやき』 木犀あこ
- 『普通と各停って、違うんですか』 山本巧次
- 『雨の日の探偵』 階 知彦
- 『神々の計らいか?』 吉田恭教
- 『虫』 結城充考
- 『監禁が多すぎる』 白井智之
- 『チョコレートを嫌いになる方法』 辻堂ゆめ
- 『銀河鉄道で行こう!』 豊田巧
- 『方向指示器』 小林泰三
- 『庭をまもるもの』 須賀しのぶ
- 『寅さんの足はなぜ光る』 柴田勝家
- 『脱走者の行方』 黒岩 勉
- 『日常の謎の作り方』 坂木 司
- 『味のないコーラ』 住野よる
- 『鍵のゆくえ』 瀬川コウ
- 『彼らはなぜモテるのだろうか……』 市川哲也
- 『やみのいろ』 中里友香
- 『インデックス化と見ない最終回』 十市 社
- 『文系人間が思うロボットの不思議』 沢村浩輔
- 『街道と犬ども』 石川博品
- 『沖縄のてーげーな日常』 友井 羊
- 『ジャンルという名の妖怪たち』 ゆずはらとしゆき
- 『カロリー表示は私を健康に導くのか』 秋川滝美
- 『終電を止める女』 芦沢 央
- 『女子クラスにおける日常の謎』 櫛木理宇
- 『IBSと遅刻癖』 岡崎琢磨
- 『シューズ&ジュース』 青崎有吾
- 『キャラが立つとは?』 東川篤哉
- 『「源氏物語」のサブカルな顔』 荻原規子
- 『そこにだけはないはずの』 似鳥 鶏
- 『『美少女』に関する一考察』 加賀美雅之
- 『食堂Kの謎』 葉真中顕
- 『寒い夏』 ほしおさなえ
- 『人喰い映画館』 浦賀和宏
- 『あやかしなこと』 平山夢明
- 『あなたの庭はどんな庭?』 日明 恩
- 『日常の謎がない謎』 小松エメル
- 『影の支配者』 小島達矢
- 『「五×二十」』 谷川 流
- 『グレープフルーツとお稲荷さん』 阿部智里
- 『ボールペンを買う女』 大山誠一郎
- 『日常の謎の謎』 辻真先
- 『『サイバー空間におけるデータ同定問題』あるいはネット犯罪量産時代』 一田和樹
- 『囲いの中の日常』 門前典之
- 『カレーライスを注文した男』 岸田るり子
- 『お前は誰だ?』 丸山天寿
- 『世界を見誤る私たち』 穂高 明
- 『名探偵は日常の謎に敵うのかしら?』 相沢沙呼
- 『で、あなた何ができるの?はあ、皇帝だったらたぶん…』 秋梨惟喬
- 『すっぽんぽんでいこう!』 桜木紫乃
- 『右腕の長い男』 麻見和史
- 『坂道の上の海』 七河迦南
- 『彼女は地下鉄でノリノリだった、という話。』 柴村仁
- 『その日常で大丈夫か?』 汀こるもの
- 『成功率百パーセントのダイエット』 小前亮
- 『謎の赤ん坊』 蒲原二郎
- 『一般人の愚痴と疑問』 沼田まほかる
- 『寄る怪と逃げる怪』 高田侑
- 『福の神』 木下半太
- 『マッドサイエンティストへの恋文』 森深紅
- 『私の赤い文字』 大山尚利
- 『となりあわせの君とリセット』 詠坂雄二
- 『美人はなぜ美人なのか』 小川一水
- 『なぜモノがあるのか。』 鈴木光司
- 『この目で見たんだ』 北村薫
- 『運命の糸が赤いのは?』 山下貴光
- 『念力おばさん』 湊かなえ
- 『方向オンチはなぜ迷う?』 山本弘
- 『ゆがむ顔のカルマ』 真藤順丈
- 『子供だけが知っている』 宇佐美まこと
- 『人はなぜ、酒を飲むのか』 薬丸岳





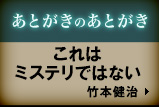


 メフィスト 2020 vol.2
メフィスト 2020 vol.2 メフィスト 2020 vol.1
メフィスト 2020 vol.1 メフィスト 2019 vol.3
メフィスト 2019 vol.3 メフィスト 2019 vol.2
メフィスト 2019 vol.2 メフィスト 2019 vol.1
メフィスト 2019 vol.1 メフィスト 2018 vol.3
メフィスト 2018 vol.3 メフィスト 2018 vol.2
メフィスト 2018 vol.2 メフィスト 2018 vol.1
メフィスト 2018 vol.1 メフィスト 2017 vol.3
メフィスト 2017 vol.3 メフィスト 2017 vol.2
メフィスト 2017 vol.2 メフィスト 2017 vol.1
メフィスト 2017 vol.1 メフィスト 2016 vol.3
メフィスト 2016 vol.3 メフィスト 2016 vol.2
メフィスト 2016 vol.2 メフィスト 2016 vol.1
メフィスト 2016 vol.1 メフィスト 2015 vol.3
メフィスト 2015 vol.3 メフィスト 2015 vol.2
メフィスト 2015 vol.2 メフィスト 2015 vol.1
メフィスト 2015 vol.1 メフィスト 2014 vol.3
メフィスト 2014 vol.3 メフィスト 2014 vol.2
メフィスト 2014 vol.2 メフィスト 2014 vol.1
メフィスト 2014 vol.1 メフィスト 2013 vol.3
メフィスト 2013 vol.3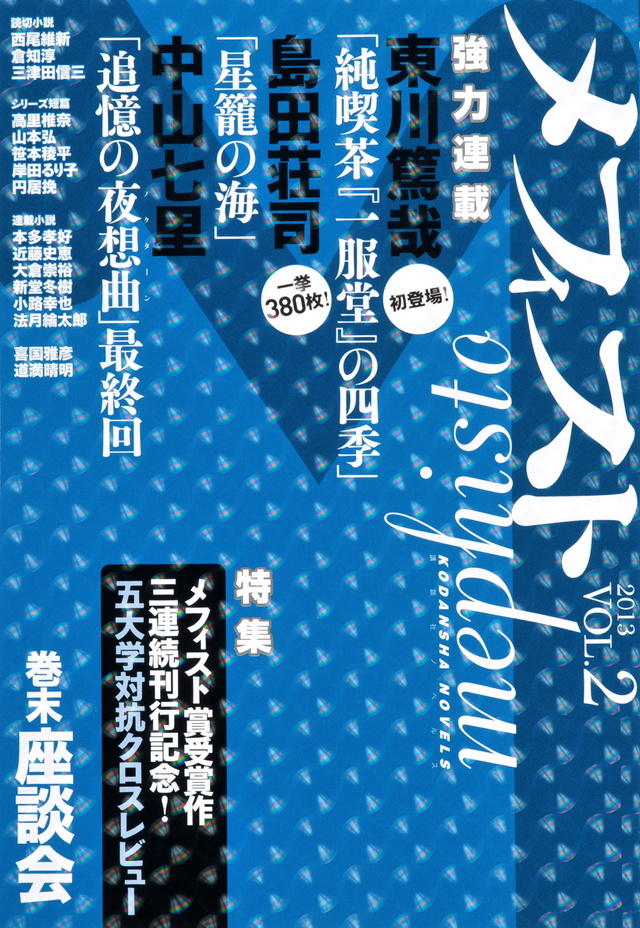 メフィスト 2013 vol.2
メフィスト 2013 vol.2 メフィスト 2013 vol.1
メフィスト 2013 vol.1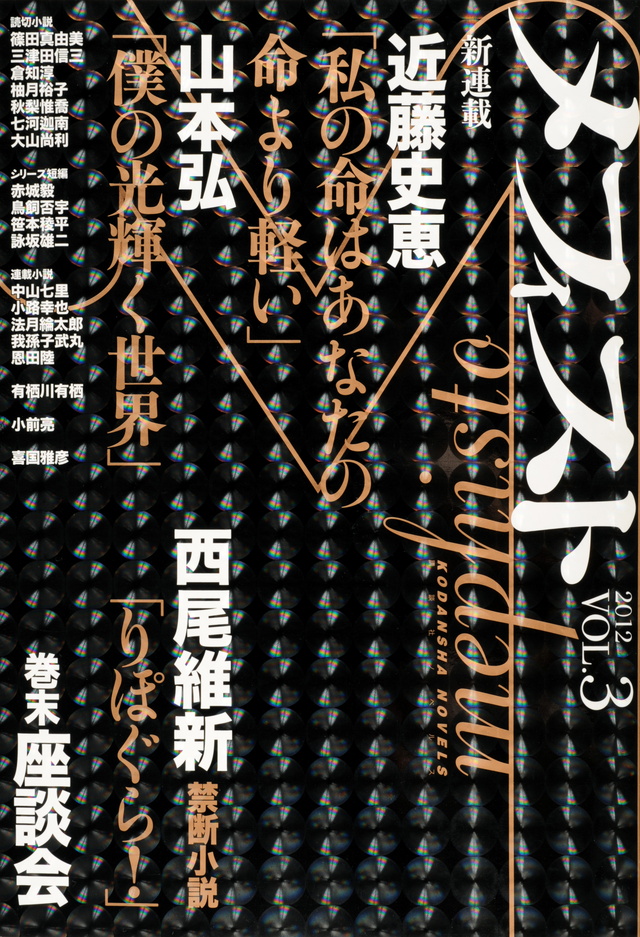 メフィスト 2012 vol.3
メフィスト 2012 vol.3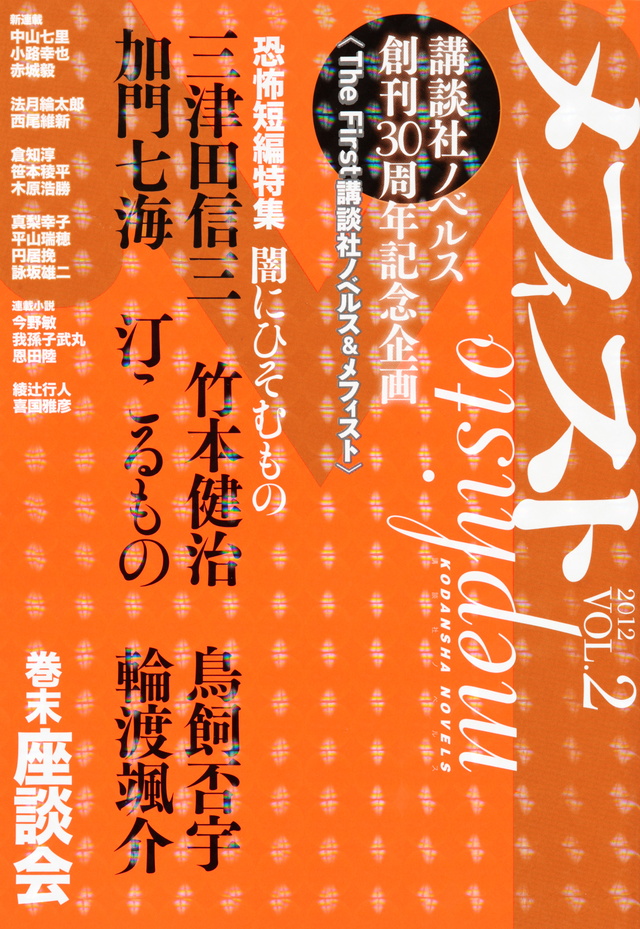 メフィスト 2012 vol.2
メフィスト 2012 vol.2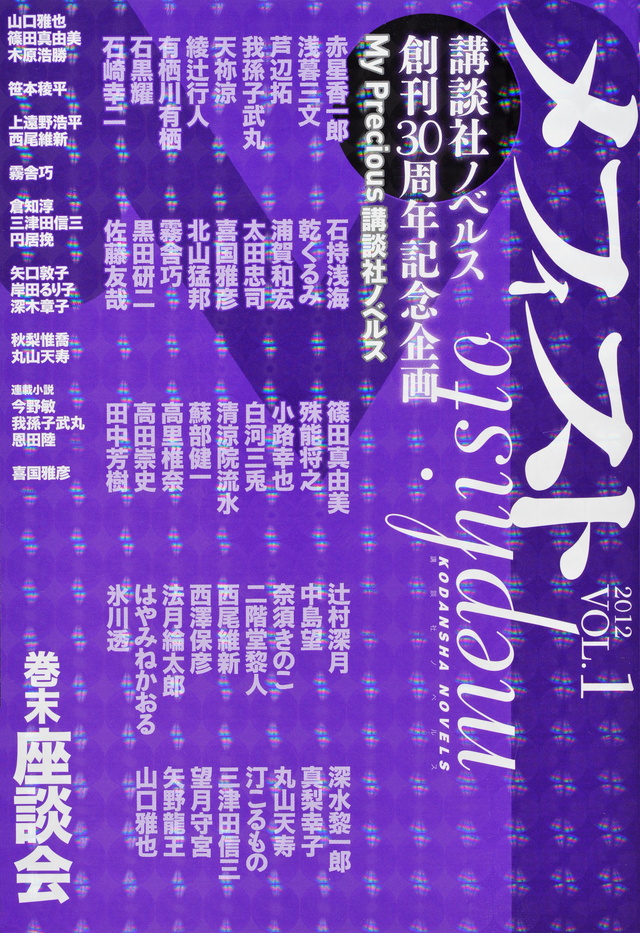 メフィスト 2012 vol.1
メフィスト 2012 vol.1 メフィスト 2011 vol.3
メフィスト 2011 vol.3 メフィスト 2011 vol.2
メフィスト 2011 vol.2 メフィスト 2011 vol.1
メフィスト 2011 vol.1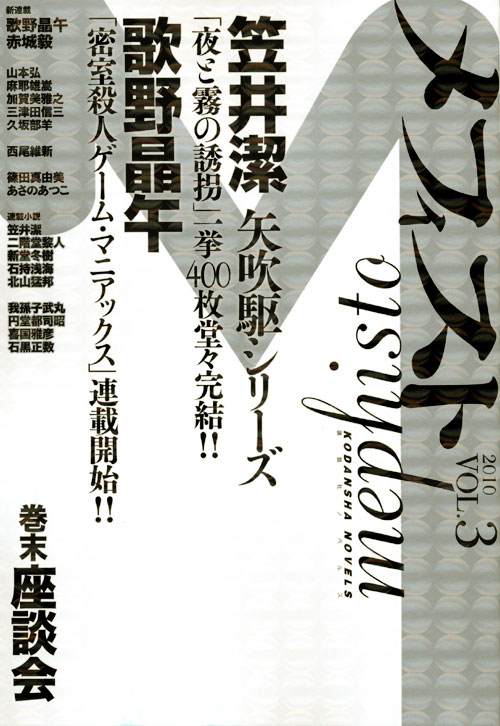 メフィスト 2010 vol.3
メフィスト 2010 vol.3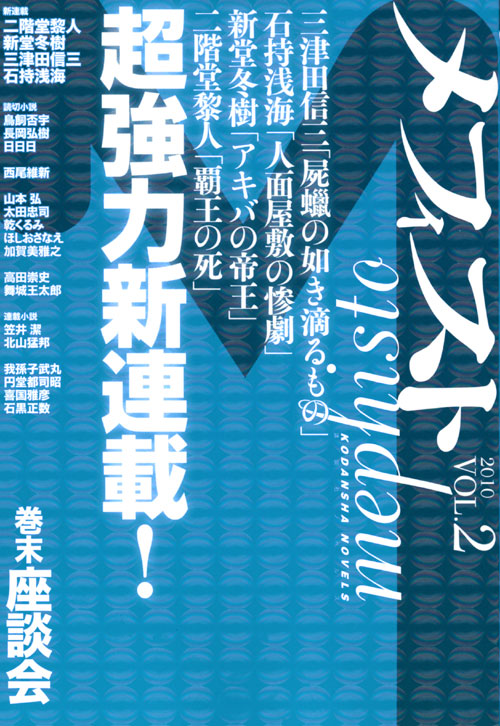 メフィスト 2010 vol.2
メフィスト 2010 vol.2 メフィスト 2010 vol.1
メフィスト 2010 vol.1 メフィスト 2009 vol.3
メフィスト 2009 vol.3 メフィスト 2009 vol.2
メフィスト 2009 vol.2 メフィスト 2009 vol.1
メフィスト 2009 vol.1




