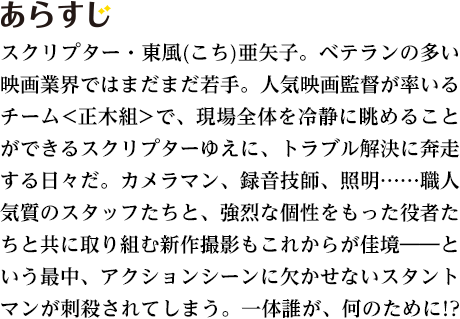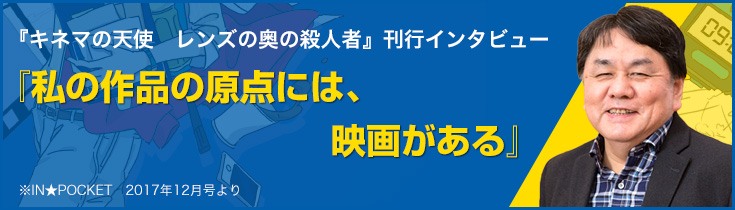──有名なスクリプターもいらっしゃるんですか。
赤川 スクリプターは本当に縁の下の力持ちなので、ほとんど有名な方はいないんですが、唯一、黒澤明さんのスクリプターだった野上照代さんという方。あの方は名物スクリプターで、本も出していますね。ほかにもいくつか読みましたが、大体、恐そうなおばさんなんですよ、やっぱり(笑)。亜矢子みたいな若い人はあまりいない。
──今は少なくなってしまったと聞きました。
赤川 フィルムの時代には映像を撮ったあと、映像と音がずれないようにするにはスクリプターが絶対必要でした。それがデジタルの時代になって、今、スクリプターなしの現場が増えていると聞いていますね。ただ、スクリプターの仕事って本来は記録するだけじゃないので、本当はやっぱりいてくれたほうがいい。人件費削減で、助監督にやらせてしまう現場も出てきているというので、ちょっと淋しいなと思いますね。
──今回の作品はミステリーであると同時に、スクリプター亜矢子のお仕事小説でもありますね。
赤川 スクリプターはあんなこと、本当はやりませんけどね。崖から吊されたりとか(笑)。監督にいかに気持ちよく仕事してもらうか気を遣う仕事ですね。撮影全体を見ながら、今どれぐらい撮っているか、進行具合も把握しておく。
脚本が出来た時には、プロデューサーはまずスクリプターに聞くんですよ。これ何時間ぐらいになります?って。それが分からなきゃいけない。
──脚本を読んで、間(ま)も計算できる。
赤川 読んで自分で台詞言ってみて、画面で何分になるな、と。全体で何時間かかるから、これぐらい切らないとダメですよと言うのはスクリプターの仕事なんですね。相当に映画のことを分かっていないと務まらないんですよ。だから若い人には難しい。何十年も現場を経験して、監督が迷っている時には、こうしたらいいですよと、それぐらい言えなきゃいけないんです。
──亜矢子も、監督の無茶な要望に応えつつ、言うべき時は言うところがかっこいいなと思いました。
赤川 同じ場面を何回やり直しても上手くいかないときに、「他の場面を先に撮っちゃったら?」とアドバイスしたり。そうすると気分が変わって上手くいったりする。映画に関する相当の知識と愛情がないと務まらない仕事ですね。単にデジタルになったからもう要らないという発想は、スクリプターを分かっていないなと思うんですけどね。いいスクリプターの場合、この監督にはこの人って、ほとんど決まっています。黒澤さんにはいつも野上さん、とか。女房役なんですね。
赤川さんと映画
──赤川さんは小さな頃から映画をよく観ていたそうですね。
赤川 そうですね。父は戦時中、満洲で満映(満洲映画協会)にいましたので、博多に引き揚げてきてから、そのまま東横映画(株式会社)という、後の東映ですが、その会社の九州支社長になりました。
といっても本当に小さなところで、下が会社で2階が家になっていて。その2階で産婆さんに取り上げられたのが私でした。その後さすがに一軒家に引っ越しましたけれど、小さい頃は下が会社だったから毎日のように映画を観ていましたね。
――ご自宅が映画館のようなものですね。
赤川 東京からフィルムが送られてくるんですね。映画1本ってフィルム何巻もあって、間が1巻抜けていたりしたら大変です。全部揃っているか、キズがないかなどを確かめるために試写をするんです。それを小さい頃からずっと観ていましたね。
──特にお好きだった映画は何ですか。
赤川 当時、東映はチャンバラ映画でしたからね。市川右太衛門という、北大路欣也さんのお父さんが「旗本退屈男」というキャラクターで、眉間に三日月の傷がある役をやっていて、よくおもちゃの刀を腰に差して、母親の口紅で眉間に傷を描いて遊んでいたそうです。幸い記憶はないんですが(笑)。
市川右太衛門と片岡千恵蔵の2人が東映の御大と言われる人たちで、その後に中村錦之助が「紅孔雀」などで、紅顔の美少年として出てきたんですね。そういうのをずっと観て育ちました。私の作品の原点には、映画があると思います。
中学ぐらいから外国の映画を観るようになって、日本の映画はほとんど観なくなっちゃったんですけどね。
撮影現場の昔と今
──撮影現場に実際に行く機会もあったのでしょうか。
赤川 父が東映の東京本社に移って教育映画部の部長だった頃に、そのロケについて、日光だったかな、木造のすごく古い小学校でのロケに、行ったことがあります。小学校の3~4年生の時ですかね。スタッフの人に、出てみません? と言われて、いやだ、と言った憶えがある。
教育映画というのは、学校で行事として上映したりする映画ですね。本当にお金をかけないで、16ミリで撮る、50分ぐらいの映画なんですけどね。
──それが初めての映画の現場ですね。
赤川 そうですね。当時の東映の教育映画って結構いい作品があります。「六人姉妹」という作品は、父が「企画」で名前が出てくるんですけど。当時の綴り方(作文)コンクールで入賞した作文をもとにして作った映画で、三女を演ったのが本間千代子という、後にアイドルになった子です。その時はもちろん全く無名なんですけどね。
現場を詳しく見るようになったのは、やっぱり作家になってから、大林宣彦さんの「ふたり」ぐらいからですね。「セーラー服と機関銃」のときは、ちょっと行ってグラビア用に写真を撮ったりするだけでしたから、実際に現場を見るという雰囲気じゃなかったんですが、「ふたり」では、尾道まで行って、泊まって、しばらく見物したりしていました。
──どのような印象がありましたか。
赤川 あぁこういうふうに撮るのね、という感じでしたね。といっても大林さんの現場は、ちょっと特殊だったと思いますけれど。地元もすごく協力的で、エキストラはみな無料で出演してくれたり。
──大林監督のお名前も出ましたが、『キネマの天使』の正木監督も印象的なキャラクターですね。
赤川 多少大林さんっぽいところもあります(笑)。今どきいません、ああいう監督。
──笑ってしまったのは、亜矢子が殺されかけて電話をかけてきた時に、「そうか。で、どれぐらいでこっちへ来れる?」って(笑)。
赤川 映画の現場って、そういうところがありますからね。監督はなにしろ一番偉い訳ですから、無茶苦茶言うんですよね。でもあれは一昔前の監督で、今の監督はそんなことないですね。大体、役者を見ていないんです、モニターを見ていて。以前、ある撮影を見に行きましたけど、撮っている所と離れた部屋で監督がモニター見ているんですよ。へーえ、こんな風になっちゃったんだなと思いました。
──「カット!」の声を掛けるのは……。
赤川 その部屋で掛けるんです。大声で言えば聞こえる距離なので。
でも大林さんは今でも絶対、それはやりませんね。やっぱり目の前で役者の演技を見ないと。先日もドキュメンタリーで、大林さんが映画を志している若い人たちに話をしていましたが、「モニターを信じちゃダメだよ」、「モニターは嘘つくからね」とおっしゃっていましたね。大林さんは役者にも見せないです。OK出すのは監督なんだから、役者は見なくていいということで。本来はそうなんですね。
──もともとフィルムだった頃はその場では見られない。
赤川 現像しなきゃいけないから、どんなに急いでも翌日にならないと見られないわけです。その場では分からない。だから、監督がOKを出す時は一種の賭けなんですよね。監督だって、どう映っているか、全部知っているわけじゃない。でもそこに映画の良さがあると大林さんはいつも言ってます。そういう人は今、本当にいなくなりましたね。
──映画の現場も変わってきているんですね。
赤川 ここに出てくる監督やスクリプターの仕事の仕方は、カメラマンなども含めて、スタッフが職人気質で仕事をしていた頃の映画の現場というつもりで書きました。これが今かというと、多分そうではないと思います。
──助監督をはじめ音声さん、照明さんなども登場します。
赤川 現場はこうじゃないですよ。もっとすごい人数いますからね。カメラマンだって音声さんだって、助手が沢山います。それを書いていたら大変なことになっちゃうから、一応、一人ずつみたいな感じで書いてありますけど。
──多くの方が集まって力を合わせて作っている映画の現場の空気を感じました。
赤川 独特のものですよね。最後に皆で、クランクアップの記念写真を撮って、それでパッと別れたらもうみんな、それぞれ違う現場に行くわけですよね。
──それまで何十日かは家族以上に親密に過ごした人たちですね。
赤川 一つ釜の飯を食うというか、皆で生活している。よほどの大作は別として、低予算で作っているものなんて、ほんとに学生の合宿みたいなものですからね。不思議な世界ですね。そういう雰囲気が少しでも分かってもらえればいいなと思っています。映画を観る時にそういうことを知っていると少しは面白いんじゃないかと思うんですよね。
まあ今どきあまりいない人たち、消えつつある映画の世界という設定ですけれど、いい時代の映画の作り手たちの気持ち、雰囲気みたいなのを書いておきたいなと思ったんです。
──消えつつある世界を書いて残しておく。
赤川 そうですね。私自身、そんなに詳しいわけではないし、実際にスクリプターさんに取材したわけでもないので、実際と違う事は沢山あると思うんですけど、ただ、映画に対する思いなどは多分そんなに違っていないと思っています。
※この続きはIN★POCKT 2017年12月号でお楽しみください!