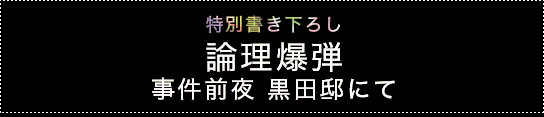
──ああ、全部聞いていたよ。〈水無月〉という探偵名のお母さんが、五年前にそこで消息を絶ったんだろう。その調査に向かった花隈慎二(はなくましんじ)という探偵も同じく行方がわからなくなってしまった。深影村には何か秘密があるんだろう。深い影という名が暗示的で不吉に思える。
伊都子は、アルコールの力を借りて対話をする。
──罠が仕掛けられているのかもしれません。それが五年後の今もあるのかどうか。
──安全だという保証はないね。ところで、その罠とやらは誰が仕掛けたと言うんだい?
──政府でしょう。〈水無月〉が追っていたのは、韮川士郎(にらかわしろう)というフリーのルポライターが密室で怪死した事件です。韮川は、世界中にセンセーションを巻き起こすような何かを取材していたようですから、国家機密に手を伸ばしていたのだと思います。
──たかがフリーのルポライターを沈黙させるのに、政府が殺人を犯すだろうか?
──ありえる、とご存じのくせに。
夫の口元に皮肉な笑みが浮かんだ気がした。
──無事を祈りながら、見守るしかありませんね。できることがあるかもしれないので、手を貸してあげるつもりです。あなたに習ったやり方で。
──それがいい。ただし、くれぐれも注意を怠らないように。
「失礼しますよ」と言ってから、写真の前のグラスからウィスキーを飲んだ。
酔いが少し回ったところで、電話機を片手にソファに戻り、真行寺晴香にかけた。純と話したことを聞かせる。
「やっぱり行くんですね、あの子」
晴香は、やや硬い声で言った。
「ええ、朝早くにうちを出て行きます。大濠公園をいっしょに散歩する暇もありません。あなたが予想していたとおりでしょう。期待していたとおり、かしら?」
「期待だなんて……。わたしも心配しています」
かつての教え子は、軽い抗議口調になる。
「ええ、心配ですね。だけど、〈水無月〉の身に何が起きたのか知りませんけれど、あれからもう五年もたっています。危険が去っていることを祈りましょう」
「危険は去って、手掛かりは残ったままだといいんですが」
「残っていたとしても、それをあの子が見つけられるかどうか怪しい。探偵志願者というだけで、まだ素人ですからね」
晴香はそれに同意した上で、「ですが」と言った。
「押井の周辺で起きた殺人事件で、あの子は探偵をやってみせました。きれいに事件を解決させたわけではありませんが、トリックを見抜いて犯人を指摘しています」
「その話は、この前の電話で聞きました。歩いているうちに犬が棒に当たったのでは?」
晴香は強く否定する。
「いえ、そうではありません」
「晴香ちゃんもあの子も、それを過大に評価していませんか? 探偵名は〈ソラ〉だそうですね。まだよちよち歩きの雛のくせに、探偵名だなんて」
わざと刺激するように言ってみると、晴香は反論した。
「仲介の仕事をするうちに、わたしは探偵の素質を見る目が養えたと思っています。純は、探偵になるための大切な何かを持っています。まだ『何か』としか言えませんが」
「わかりました。覚えておきましょう」
晴香はさらに言う。
「母親にたどり着く過程で、あの子が立派な探偵に成長してくれることを望んでいます。それだけじゃありません。わたしは、ソラに日本を変えてもらいたいんです。この国の未来を創ってもらえたら、と……」
「さすがにそれは過大な期待ですね。荷が重すぎて、あの子は押しつぶされますよ」
電話を切った後、伊都子はグラスを静かに空けた。
──自分だってまだ三十代半ばのくせに。日本の未来を創るために、あなたもがんばりなさい。
そんなふうに晴香を叱ってやればよかった。
と、夫の声を聞いた気がした。
──もうすぐ七十のきみにも何かできるだろう。ぼくと違って、生きているんだからな。
「そうですね。あなたの言うとおり」
もう一杯、飲みたくなった。