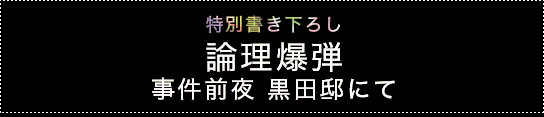
時計の音が広いリビングに響く。二つのティーカップは、とうに空になっていた。
「好きな男の子は、いますか?」
さびしさを癒してくれる存在がいればいいのだが、と思いながら訊いてみたのだが──。
「遠くにいます」
やるせない答えが返ってきて、会話がとぎれてしまう。
「紅茶をご馳走さまでした。明日は早いので」
純は、立ち上がって一礼した。
「色々とお世話になり、ありがとうございました。おやすみなさい」
「そう。おやすみなさい」
純が出て行くと、伊都子は部屋着にしている紫色のドレスの裾をさばきながらサイドボードに寄り、ウィスキーのボトルを取り出して、グラスに二杯、少しずつ注いだ。一つをマントルピースの写真の前に置き、もう一つを立ったまま飲む。
「あの子のこと、どう思いますか?」
写真の夫に問いかけた。
「このご時世に探偵になりたいんですって。わたしたちの孫みたいな十七歳の女の子が、探偵ですよ」
夫は険しい表情をしていた。妻の展覧会場に大勢の人がきてくれたことを喜んでいたときの写真なのに、胃痛でもこらえているかのような表情だ。悪い癖で、カメラを向けられるといつもこの顔になった。波が砕ける磯の岩場を描いた絵を背景にしているので、憂悶する哲学者のように見える。実物は渋(しぶ)い二枚目だったのに。披露宴で、まれな美男美女のカップルだとうらやましがられたのが懐かしい。
伊都子は今年で七十歳。六年前に死んだ夫の年を五つも越えてしまった。美しく老いること。昨今、それが最大の関心事だ。
「応援してあげたいと思うんです。先輩として、恭三(きょうぞう)さんだったらどうしますか?」
空閑純の両親と同じく、黒田恭三もこの国では法律で禁止された探偵だった。純の父〈調律師〉や母〈水無月〉と違い、金銭的な報酬は得ていなかったが、警察を信じられない依頼人のために卓抜した推理力を使っていた。無免許の医師が報酬を受け取らなくても処罰されるように、それもまた明白な違法行為だった。
警察類似行為、俗にいう私的探偵行為を日本政府は認めない。犯罪捜査は国家権力が一元管理しなくてはならない、一般人が警察を凌駕する犯罪解決能力を持つことは危険である、という奇怪な思想からできた法律だ。抑圧的な政府は、市民が自由に知恵を働かせることを憎む。
その法律が施行されて以来、探偵は犯罪者となり、社会の表側から消えた。〈調律師〉や〈水無月〉のように地下にもぐって活動を続けた探偵もいたが、恭三はその才能を発揮するのを控えた。美学・美術史の泰斗としての名声、大学教授の地位、そして妻との平穏な暮らしを守るために。
──でも、わたしに内緒で少しはやっていたでしょう? 困っている人に相談をもちかけられて、あっさり断れる人ではありませんものね。探偵としての能力を埋もれさせることが惜しかったでしょうし。
伊都子は、写真に向かって微笑した。いつだったか、夫のスーツのポケットに謎めいたメモが入っているのを見つけたことがある。ふつうの夫婦なら浮気を疑うところだが、伊都子の目にはある人物のアリバイ工作を崩すためのものだとわかった。油彩画家であると同時に、彼女は恭三の優秀な助手でもあり、夫ほど鋭いものではないにせよ探偵の目を備えていた。
──明日、深影村(みかげむら)に行くそうです。宮崎県の山奥。平家の隠れ里だったという伝説がある村ですよ。
写真の前に置いたグラスを傾けながら、夫が話し始めるような気がした。ウィスキーに目のない人だった。